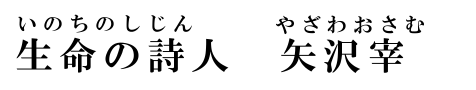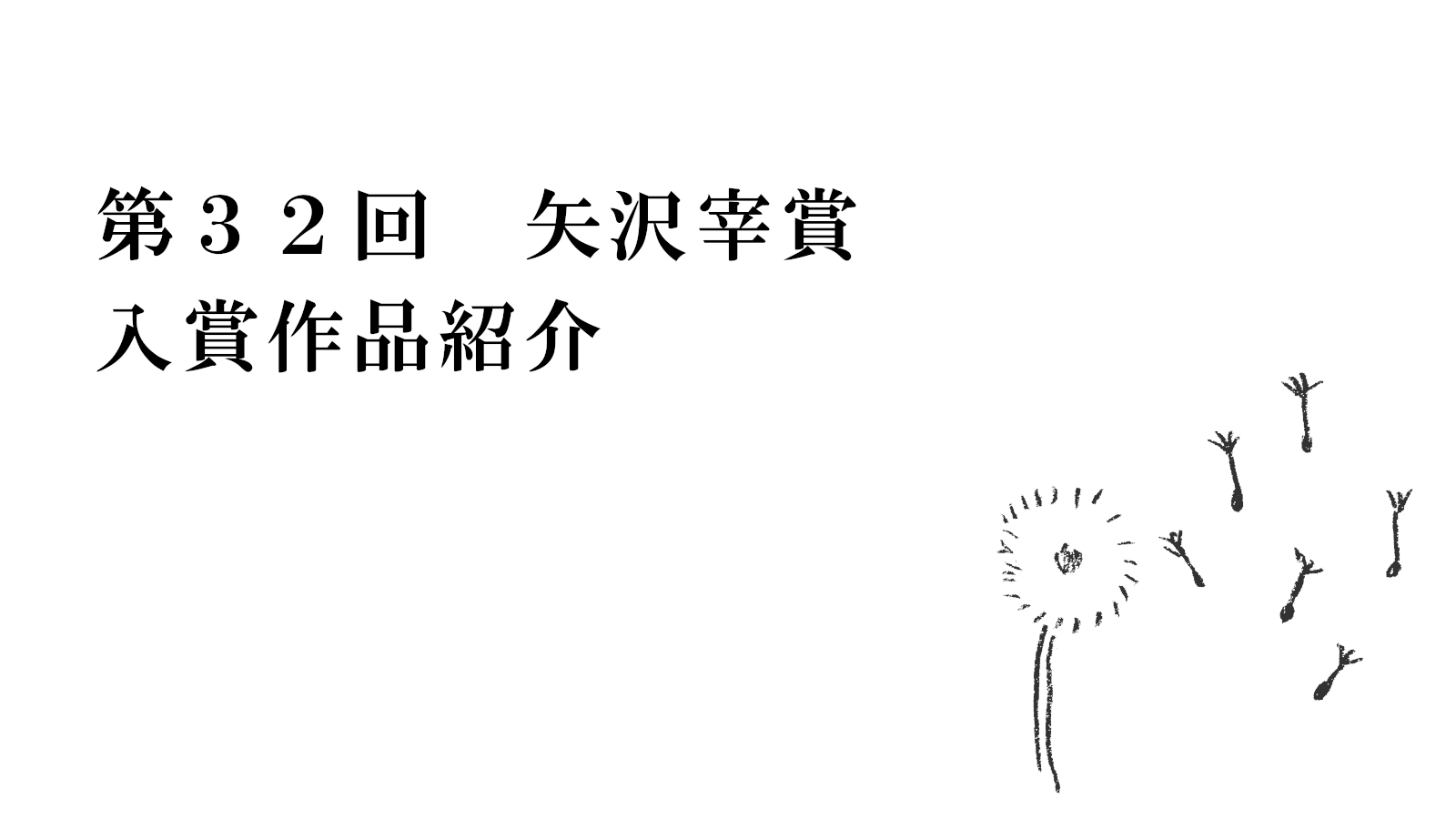最優秀賞
最後のステージ 福井 聖斗
(熊本県立盲学校高等部3年)
大きなホールに立った
ライトがまぶしい
心臓がバクバクして
息がふるえそうになった
でも 仲間の顔を見て
安心して息ができた
中学部から続けた アンサンブル部
マリンバ ビブラフォン ティンパニー
いろんな楽器を経験した
放課後の練習の日々
一つひとつの積み重ね
仲間と共に高め合う
時にはぶつかりもしたけれど・・・
演奏開始のブレスを聴くと
身体が自然に動いていった
さっきまでの緊張が 嘘のよう
仲間の音を聴き
仲間と心をひとつにして
ようこそ
私たちの音楽の世界へ
観客の大きな拍手
自然と胸が温かくなった
やりきった
高校最後の大きなステージ
でも終わりじゃない
この経験は
未来につながっていくんだ

アンサンブル部、最後の発表の大きなステージなのであろう。ホールに立って、心臓はバクバクして震えそうだけれど、辛かった練習の日々を思い出して、落ち着こうとつとめる。演奏開始。「仲間と心をひとつ」にする。これが肝腎なこと。終われば、「私たちの音楽の世界へ」「ようこそ」である。「観客の大きな拍手」で報われるけれど、これで終わりにせず、これを「未来」につなげて行きたい。それが厳しい現実。
2020年新潟県知事賞受賞
これでも若くてうらやましいですか 野田 惺
(大阪府立中央聴覚支援学校高等部2年)
用もないのにまたスマホ
みんなキラキラしてるリア充ばっかり
私も楽しまなきゃ、充実しなきゃ
焦ってジタバタ
友達と遊んだら刺激を受けて疲れるのに
今日もまた予定を入れた
わかってる
「楽しい!幸せ!最高!」
インスタに載っているのはその一瞬だって
「しんどい、だるい、うざい」もある
でもみんなそれは載せない
隣の芝はどこまでも青い
「かわいい、綺麗、細い」
目に見えるものが重視されるこの世の中
いつの間にか、のまれてしまったみたい
「見た目より中身よ」なんて
今の私に届かない
みにくい心を脱ぎ捨てて
どっか遠くに行ってしまいたい
もうわたしは一人の人間として
意見があるし意志もある
でもまだ学生でお小遣いをもらってる
学費だってスマホ代だって払ってもらってる
「おこづかい」その響きが
子どものしるしみたい
まだ映画で泣いたことがない
自分のことならこんなにも涙があふれるのに
隠しきれないこの幼さ
早く大人になりたい
大人になってしまいたい
でも一人の大人として見られるのが
怖くて心細くてまだ甘えていたくて
ちっぽけな私の満されない心をもてあます
17の夏
「そんなときもあったね」って
多分、未来のわたしが笑ってる

「リア充」とは「リアルに充実している」の意と欄外に註記されている。みんなスマホをのぞいている。しかし、作者は遠くで自分の意見や意志そのものを示したい。まだ親がかりの子どもである。「大人になってしまいたい」というのが本音だ。まだ「ちっぽけな」私は満たされない心をもてあましている。未来の私が笑っているかもよ?
奨励賞
一歩 田村 百合葉
(前橋市立箱田中学校2年)
はじめの一歩
うれしいからの一歩
めんどくさいからの一歩
くやしいからの一歩
ずんずん
ちょこちょこ
だんだん
ぴょこぴょこ
「一歩」は人それぞれだから
くやしいからの一歩
逆境からの一歩
勇気を出して一歩
大きく一歩
どんな一歩でも
自分が成長する「一歩」になる
大きな一歩を大切に
だって、一歩を積み重ねて
人生という長い長い短いみちを
創っていくのだから

いろいろな状態にある一歩、人がそれぞれに歩いてゆく。それが「成長する一歩になる」という。一歩一歩は地味だけれど大切なのだ。そのことを作者はくり返し書いている。人生は一歩一歩の積み重ねである。人生は長いようではあるけれど、その道のりは長いようで短い。それを作者は「長い長い短いみち」と表現しているのである。
夏の記憶 菊池 心春
(見附市立南中学校1年)
夜空に咲いた 一つの華
音の余韻が 降りそそぐ
胸に残った あの姿
誰かの心に 響かせた
浴衣の裾が ひらひらと
風にあおられ 背中を撫でる
屋台の灯りが 夜を染めて
りんご飴が 赤い月になる
窓辺で鳴った 自然の音
外を眺めて 心がほどける
ちいさな鈴が 風に揺れ
ガラスの瞳が 夏を映し出す

夏の花火の夜の記憶を書いているのだろうけれど、「花火」という言葉は使われていない。第一連で表現されているのは「華」であり「音」である。花火を表している。第二連の「浴衣の裾」や「りんご飴」「赤い月」で、会場の情景を描き出す。第三連で情景をさらに展開している。一種の静けさのなかに、花火の夜の美しさが十分描かれる。
雨あがり 石川 心海
(前橋市立箱田中学校2年)
雨がやんで
道に小さな
ぽつぽつと
光のつぶ
空が泣いてごめんねって
言っているみたいだった
ぬれたくつで
そっと歩いたら
どこかで
風がうたってた
水たまりに
うつった空が
「だいじょうぶ」って
いったきがした
いつもより
ちょっとだけ
世界が
やさしくみえた
足あとを
ふみしめるたびに
ぴかりと光が
はねあがる
すこしだけ
ぬれた心も
風がそっと
かわかしてくれた
わたしは
また、あしたに
歩き出した

雨も空もやさしそうにとらえている。光のつぶもぴかりとはねあがって可愛いし、風もうたっている。雨あがりだからだろう。作者はうきうきと、雨があがったのをたのしんでいるようだ。雨の降りはじめだったら、こうはいかないだろう。濡れた心を、風が気持ちよくかわかしてくれる。終連の三行で、明日にむかって元気よく歩き出す。
入選 (50音順)
かたちのない平和 安 飛霏
(文京区立茗台中学校2年)
平和は
目で見ることができないものだと思う。
それは風のように
町をふきぬけて
ちょっとあたたかさを残す。
それは水のように
かわいた大地にしみこみ
心のすきまをうめていく。
それは時間のように
見えないけれど
毎日の中を流れて
みんなを生かしてくれる。
だれかは「平和=戦争がないこと」と言うけどわたしは思う。平和とは、手をさし出したときに心の中にひびく音なんだ。

平和は「風」「水」「時間」のようだと作者は言う。それは人によって違うだろう。そんなことは作者も知っているのだ。かたちは見えないが、「心の中にひびく音」というとらえ方。
喜びの中で 五十嵐 文華
(蓮田市立黒浜中学校2年)
スクリーンをかけた
ゴール下で 身体を張った
けど ボールは来なかった
何かを残せた気が しなかった
試合が終わった
スコアは勝ってた
みんな 笑ってた
ベンチも コートも 歓声に包まれてた
でも 自分の中は ちょっと静かだった
試合中、コートのすみっこで
自分にできることを探してた
スクリーン カバー 走ること
小さなことばっかりだったけど
手を抜こうなんて 思わなかった
でも正直、嬉しさと悔しさが
ぐちゃぐちゃになってた
ハイタッチしながら
「おめでとう」と「ごめん」が
胸の奥でぶつかってた
けど、ふと 仲間が言った
「あのリバウンド、よかったよ」って
それだけで 少し救われた
見てくれてる人は ちゃんといる
今日はチームが勝った日
自分の力は ほんの少しかもしれない
でも ゼロじゃなかったって
そう思えたから 前を向けた
次は もっとコートで叫ばれるような
そんなプレーを してみせる

バスケットの試合だろうか。試合には勝ったけれど自分は不本意に終わって、気持ちがすっきりしない。嬉しさと悔しさ。しかし、仲間の言葉で救われた。次のプレーで頑張ろう。
私のすべて 石川 木の葉
(見附市立上北谷小学校6年)
私のハムスター
名前はおもち
私はハムスターを飼うことが夢だった
そして私はお父さんに
「ハムスターを飼いたい!」
と言ったらお父さんは
「いいよ」
と言った
その日
私は家族とペットショップへ行った
最初に行った所はたくさんハムスターがいた
けれども
「ピーン!」とはこなかった
次のお店へ行った
ハムスターが見えなかったので
お店の人に見せてもらったしゅん間…
「ピーン!」
ときた
「この子だ!この子にする!」
とすぐに決めた
そして
私のすべてとなった
家に帰っておもちをゲージに入れた
まん丸の目で私を見つめてくれた
ハムスターのことをたくさん調べた
そして次の日私の手を
「ペロペロ」と二回なめてくれた
毎朝六時に起きておもちのエサやり
おもちは決まった時間に起きて
まるでおもちが私に
「おはよう!」
と言っているような気がする
そしておもちは毎日毎日みんなの
愛とぬくもりを感じながら
毎日を過ごしているだろう

ハムスターのおもちを「ピーン!」ときて飼った。それから「私のすべてとなった」。おもちとの日々が始まる。みんなに愛されてだんだん楽しくなるようすが、よく伝わってくる。
きれいな空 内海 凜子
(見附市立見附中学校1年)
きれいな空を見た
夕暮れ時の空だった
見た目はきれいで美しく
心の中では泣いていた
ふわっと流れた潮風は
じめじめとした
涙のかおり
すぐにでも消えてなくなりそうで
心の中で包んであげる
心の中では残ってる
きれいなきれいな空だった

あまり美しくきれいな夕空だったので、「心の中では泣いていた」。そんなこともあるもの。すぐになくなりそうな夕空だったのでしょう。やさしい心に見つめられて空も幸せです。
四季流雲 小川 栞里菜
(蓮田市立黒浜中学校3年)
ふと空をみあげてみれば
ゆったり流れる君の姿
うっかりみとれているうちに
僕の心はうばわれたようで
初夏空をみあげてみれば
少し変わった君の姿
雷雨の道を作る君を
僕はただみつめていた
秋空をみあげてみれば
みつからない君の姿
少し悲しい気持ちをよそに
僕は君の帰りをまつ
冬空をみあげてみれば
澄んだ空と君の姿
儚く流れる君の下で
僕は君の詩うたを唄う
四季が流れていくうちに
君もゆっくり空を流れる
そして僕は今日も君を想ふう

空を見あげれば、そこに「君の姿」。「君」に愛着しているのだね。題名が「流雲」だから、雲のかたちなんだ。各連に「君の姿」が頻繁に出てくるけれど、どんな「姿」なのかなあ?
守り続けたいもの 片山 綾菜
(前橋市立箱田中学校2年)
包まれているような安心するような
優しく心が温かくなる花が広がっている
緑色の中に見てほしいと必死にもがいている
桜色のように優しい色
りんりと風にまかれてゆれている
そして10年、20年
自然が静かに少しずつ姿を消していく
大きくて繊細で誠実なケヤキの木も
おおらかで恐ろしいトウヒの木も
白くて愛らしいマーガレットも
高貴で大人なスズランも
真っすくで前向きなヒマワリも
人間の力で消されていく
大好きな自然が重い碇のような
目を開けられない暗さがおそう
そして緑色はなくなってしまった
居場所がどんどんなくなっていく
とめることはできない
せまってくる時間は変えられない
どこかに静かにひそんでいる緑を
探しに行こう
守るべき存在を

ゆれているやさしい花の色。でも何年かたつうちに木も花も消えていく、人間の力によって。自然の居場所がなくなっていく。だが、それを止めることができない。緑をさがそう。
自分の居場所 川端 愛莉
(熊本県立盲学校高等部3年)
私は今 とても幸せ
自分の居場所が 見つかったから
いろんなことを学び
いろんなことに挑戦できる
盲学校という 私の居場所
以前の私は違ってた
拡大教科書を使うのは 私だけ
お前の教科書 何でそんなに大きいの?
言ってる方に悪気はなくても
言われた身には 堪えます
だんだん萎縮してしまう私・・・
なぜかいつの間にか
陰キャラグループに分類された
人は 自分と違うことを
受け入れることが 苦手のようだ
いろんな個性を認めましょう!
良く聞く言葉も 虚しいばかり
でも 今は違う
いろんな人が通っている盲学校
白杖 拡大本 拡大読書器に単眼鏡・・
個人に応じた いろんな補助具
私はここへ来て変わった
白杖を持って 一人でバスに乗る
部活動では いろんな楽器を演奏する
人前に出るのが苦手だった私だけれど
今では何と生徒会長
昔の私を知っている人は
私の変わりように 驚きを隠さない
人は 自分の居場所を見つけたとき
想像もしない力を発揮する
この学校で学び 変わっていった私
たくさんの思い出を胸に
さあ 大きな世界へ旅立とう
新しい自分の居場所を 見つける旅に

「盲学校という私の居場所」が見つかって幸せだ。以前はいろいろ言われて、つらいこともあったけれど、「ここへ来て変わった」。さらなる自分を見つけるために大きな世界へ!
風 川村 凰斗
(前橋市立箱田中学校2年)
風がひゅーひゅーひゅいんと言ってきた。
ささやくように
私たちになにかを伝えてくるようだ
風には、情がある
小さい音や大きい音
風には、個性がある
冷たい風温かい風
うるさい風や静かな風
まるで生きているかのように
風は風なりのなにかで伝えてくる
一つではない
風は、私たちと同じなんだ
私たちは、風の声は聞こえるが理解ができない
人間ではない他の生きもののように
分ってほしいのだ
風は私たちと同じように生きていることを
みんなは、風としか思ってもないし考えてもない
ただの風で終わらせている
気づいてほしいのだ
みんなに話しかけていることを
わからないけどわかる
理解できなくても
なにかを感じることができるだろう
一回ではない
何回も何回も伝えてくる
風は伝える
またどこかで

風には大きい音小さい音、うるさいものや静かなものがある。風には風の伝えたいことがある。「ただの風」ではない。何回も「話しかけていること」もある。そのことも感じよう。
雨 河谷 紗良
(前橋市立箱田中学校2年)
朝、家を出ると
泣きだしそうな雲がある
その雲は私が歩く度に
涙の量が多くなって
しまいには
私に傘をささせる程泣いてくる
私は
雲が泣くといらついてしまう
なぜならば
その涙で私がぬれてしまうから
そして、もしかしたら
他の誰かもこうやって泣いているのかなと
思ってしまうから
だから私は
泣く雲が嫌いだ
けれども
雲が泣くのは私には止められない
それほど
雲は辛い思いをしているから
だから私は
涙を傘で避けて去ってしまう
そうするたびに
ポツポツと涙が傘に落ちる音がして
いつも以上に耳が痛くなる
私はそれが嫌で足早に学校に向かうと
とてつもない罪悪感におそわれる
私は気分が悪くなって
ごめんなさい
と心の中でつぶやくと
気づいたら
冷たい涙が
あたたかい涙になったような気がした

雲にも感情があって、涙の量が多く、私を涙で濡らしてしまうことがある。誰かもそうだ。だから私は「泣く雲」が嫌い。雲の涙を嫌って罪悪感におそわれて、「ごめんなさい」。
音楽 菊地 環
(蓮田市立黒浜中学校1年)
私の声
あなたの声
みんなそれぞれ違うけれど、
全力で歌って
それが大きな声となった時
きいているひとりひとりに
思いが伝わる。
私の音
あなたの音
みんなそれぞれバラバラだけど、
全力で奏でて
それが大きな音となった時
奏でているひとりひとりに
思いが伝わる。
私の思い
みんなの思い
全員最初は別々だけど、
全力で歌って
全力で奏でて
それが大きな大きな音楽になった時
その場にいる全員
心が動かされる。

声はいろいろだけど、合わさって大きな声になって「思いが伝わる」。声は「私の思い」だったり、「みんなの思い」だったり、別々のものだったりしたものが、大きな声になる。
自分への手紙 口石 道広
(長崎県立希望が丘高等特別支援学校1年)
高校卒業後の自分へ
立派な社会人になっていますか
ちゃんと仕事はできていますか
体調の管理はできていますか
つめはきちんと切っていますか
きっと半分はできていると思います
社会人にはなれていると思います
仕事は少し心配事がいくつかあります
一つはちゃんと仕事ができるか
もう一つはちゃんと起きられるか
体調管理もできるか心配です
熱を出さないようにするには
毎日帰った後に手洗いをしてください
つめもちゃんと切ってください
頑張ってください

第一連は社会人になった自分に対する手紙。第二連六行目までは、それへの答えで、もちろん心配事もある。「立派」でなくてもいいけれど、「つめ」にこだわっている点おもしろい。
僕と妹のちがい 小菅 唯人
(前橋市立箱田中学校2年)
僕には4歳下の妹がいる
僕と妹は似ているけど違う
僕はサッカーを本格的にクラブチームで
プレーしてる
妹は体力づくりのために僕のまねをして
サッカーをしている
僕が赤ちゃんのときに最初に話した言葉は
「ブーブー」
妹が赤ちゃんのときに最初に話した言葉は
「ママ」
僕が好きな食べ物は
「アイス」
妹が好きな食べ物は
「ミニトマト」
僕の好きな季節は涼しい夏
妹の好きな季節は暖かい冬
僕の好きな教科は体育
妹の好きな教科は図工
僕の好きなラーメンの味はしゅうゆ
妹の好きなラーメンの味はみそ
僕と妹が好きなもの
「家族」だ

僕と妹とのちがいを述べている。当然と言えば当然なのだが、なぜかおかしい。同じだったらなおのことおかしい。喧嘩もするけど、きっと仲良し兄妹なんだ、それでこそ家族だ。
雨のうた 佐野 大和
(見附市立名木野小学校2年)
あめはひとりじゃうたえない、きっとだれかといっしょだよ。はなとしとしとにはなうた。かさとぽとぽとかさうた。ともだちとちゃぷちゃぷうた。ボートとばしゃばしゃうた。いるかとばしゃんばしゃんうた。うみとばしゃあんばっしゃあんうた。すいとうとちゃぽちゃぽうた。やねととんとんうた。つちとぴちぴちうた。かわとつんつんうた。あめはだれともなかよしで、どんなうたでもしっているよ。

雨はひとりじゃなくて、おおくの友だちといっしょにうたっている、そのことに目をつけて、「ばしゃあん」とか「とんとん」「ぴちぴち」と聞きとっている、耳も感性もいいのだ。
終わらない宿題 白川 航太
(十日町市立中条中学校1年)
あと一枚のプリントが、
机の隅でくしゃりと笑う。
読書感想文は題名だけ、
科学研究は名前しか書いてない
蝉の声が遠のいて、
空の青がどこか薄くなる。
日焼けした腕ももう冷たく、
心だけが熱を帯びている。
友達の声がスマホの奥で響いて、
「もう終わった?」って聞かれるたびに
なにか、大事なものを
こぼしてしまった気がした。
かすかに風が変わって、
夜が少しだけ早くやってくる。
でも、あの最後のページだけは、
どうしても埋まらないまま。

「くしゃり」と笑っている一枚のプリントは「ここまでおいで」と作者をからかっているのかもしれない。「蝉」や「空の青」を見る余裕があるじゃないか。夜がすぐやってくる。
えがおが体をおしてくる 髙橋 愛奈
(見附市立名木野小学校3年)
えがおが体をおしてくる
にっこりなかおでおしてくる
にこにこ歩くぼくらの後から
えがおな声でみんなをよびかける
にこにこ
えがおで先生がまってるぞ
えがおが体をおしてくる
そんなにおすなあわてるな
ぐるりふりむきにこにこなえがおに
ぼくらもえがおでかつんだ
にこにこ
えがおで先生がまってるぞ
またあしたもえがおで学校にいこう

題名がおもしろい。先生がえがおでみんなをまっている。何でかはわからないけれど、まっているということはいやなことではない。あしたも先生はえがおでむかえてくれ、みんなえがお。
大雨 田中 晴菜
(前橋市立箱田中学校2年)
「ピシュンピシュン」
空からたくさんの矢が降ってきた
矢は傘に刺さったり
小さな海へ落ちてゆく
一つ大きな矢が降ったとき
「コツコツコツコツ」
傘に大きくはじかれた
まるで
街中で人々が会話をしているように
たくさんの矢が飛び交う
静かな大雨の中で
傘と無数の矢の
演奏する音だけが
どこまでも続く部屋のように
音楽室で誰かが弾いたピアノのように
遠くまで響いている
風がふくと
降る向きや量を変えて
演奏を続ける
まるで
何にでも変身の出来る
くものように
どこまでも
どこまでも
進んでいく

雨を、飛び交いたくさん降る「矢」ととらえている。その音。それは演奏する音。雨と傘の音は演奏そのものである。人々の会話みたいに雨が降っている、音楽室のピアノのように。
上半身裸の男 田中 悠莉
(蓮田市立黒浜中学校3年)
今年の7月は暑かった
過去最高気温のニュースが
テレビから流れる
テレビ画面には上半身裸の男
どうして彼は上半身裸なのだろう
父が京都出張から帰った
フランスの男が上半身裸で
歩いていたらしい
父は京都は国際都市になったと言った
どうして彼は上半身裸なのだろう
母が畑から帰った
目の前に上半身裸の若い男が
歩いてきたらしい
目をそらして通り過ぎたが
母の帽子がふわりと飛んだ
上半身裸の男が拾って
「はい」と渡してくれたらしい
どうして彼は上半身裸なのだろう
私は上半身裸の男に戸惑いがある
どうして彼は上半身裸なのだろう
私は聞いてみたい
みんなは上半身裸の男を見て
どんな感情を抱くのか
私は聞いてみたい
上半身裸の男はどうして
上半身裸なのか
どうして彼は上半身裸なのだろう
どうして彼は上半身裸なのだろう

父や母が実際に経験した「上半身裸の男」との出会いから。たとえ暑いとはいえ「どうして?」か。常識では考えられない。出会ったら 「どんな感情を抱くのか」聞いてみたい。
涙 田村 心々
(十日町市立中条中学校1年)
何かがものすごく上手くいかないとき
涙が出てしまった
その時私はふと思った
涙はしょっぱいと言うけれど
感情によってしょっぱさって
変わってくるのだろうか
嬉しいときの涙、悲しいときの涙
悔しいときの涙、切ないときの涙
怒ったときの涙、苦しいときの涙
感情によってしょっぱさが
変わったとしても
自分にとって無駄じゃない涙
言葉に出来ない感情が
涙へと変わっていく

涙は一般に「しょっぱい」と言われるけれど、その時の感情によって変わってくるのではないか、というのが作者の考え方。そう、感情によって涙の味が変わっても不思議でない。
君と過ごす毎日 手島 美空
(蓮田市立黒浜中学校3年)
勉強しようと机に向かうと
すぐにノートの上に乗ってきて
「遊んでよ」って目で言うから
つい手を止めてしまうんだ
ちょっとスンとしてるときもあるけど
急にすり寄ってきて甘えてくる
その柔らかい体を感じると
なんだか心があたたかくなるよ
窓のそばで日向ぼっこしてる君を見て
わたしはふと思うんだ
毎日が同じようで違う
君と過ごす時間は特別だって
気まぐれで、わがままな君だけど
そのすべてが愛おしくて
どんなに忙しくても
君のことを考えてしまうんだ
君がわたしのそばにいてくれるから
わたしは毎日笑顔でいられる
これからもずっとずっと
君と一緒にいたいよ

「ノートの上に乗っ」たり、甘えたりする君と「同じようで違う」時間をすごしているのだが、どうしようもなく愛しくてたまらない。だから、わたしはずっと笑顔でいられる。
影 藤村 美咲
(前橋市立箱田中学校2年)
太陽が頭のてっぺんに見える頃
地面を見ると
あなたは現れていた
私のそばに
いつもいつも
今日はとくにはっきりと見える
影は私に話しかける
何も聞こえないけれど
何かを話している
前を見ると
温かいようで冷たい地面がずっと続いている
あなたとはたくさんの事を
見て
聞いて
思い出にした
あなたは私
私はあなた
心地が悪い風がふいてくる中
しとしとと水の粒が落ちてくる
とても強くやさしい雨
地面を見ても誰もいない
私はあなたに問いかける
本当のあなたはどんな人

影は私を離れようとはしない。そればかりか、「私に話しかけてくる」、その内容は残念ながらわからないけれど、水の粒に負けず「強くやさしい」内容に決まっている。影との対話。
野菜ばたけの宝物 古屋 匠
(蓮田市立黒浜中学校1年)
小さいころから 毎年春になると
土を掘って お父さんのうしろをついていく
ピーマンの苗を そっと置く
父のまねして
キュウリの苗を そっと置く
毎日水をかけながら
「はやく大きくなあれ」とつぶやく
夏になると つるがのびて
キュウリがぐんぐん 二階まで届きそう
ぼくは汗だく 虫におわれて
それでも楽しい 土のにおい
曲がったキュウリも
少し大きくなりすぎたキュウリも
小さいままのピーマンも
全部ぼくの宝物
今度は何を植えようか

お父さんと一緒の畑仕事、ピーマンやキュウリの苗を置く。「はやく大きくなあれ」と毎日水をくれる。ぐんぐん大きくなる。「土のにおい」に魅了され、野菜はおいしい宝物。
おとうとは まるい 丸山和哉
(燕市立吉田中学校1年)
おとうとは まるい
おしりも まるい
おなかも まるい
ほっぺも まるい
めも まるい
手はクリームパン
円柱だ
せいかくもまるい
みんなには まるい
ぼくには さんかく
ちょっとおかしい
でもぼくの方がおかしい
かわいくはない
でもかわいいって言われる
ごろごろしている
かわいくはない
ごろごろ ごろごろ
かわいくない

みんなが「まるい」と言うおとうとは、ぼくにとっては「さんかく」だ。みんなに同調しないで、スネているのだろうか。「かわいくはない」と言っているけれど、本当はかわいい。
僕の努力は水の泡? 三橋 奏太
(神戸市立盲学校中学部2年)
僕の一番こわいもの
静まり返る教室と
鳴り響く音 パーキンス
机の上には ぶ厚い冊子
指の下には 無数の点点
まるで 暗号
あれだけ勉強がんばったのに
過去の自分にキレそうになる
僕の努力は水の泡
僕の一番こわいもの
僕の顔は青ざめる
机の下で 地じ団だん太だをふむ。
指の下の 点が表す
僕の期待を裏切る数字
なぜ、ここミスる?
今なら解けるこの問題
僕の努力は水の泡
僕の一番こわいもの
教室に響く先生の声
いつものように流れる時間
いつものように始まる授業
テスト直前総復習
僕の努力は・・・
水の泡?
本当に?
そんなわけない!
人生で大活躍する
素晴しい知識
僕の一番こわいもの
それは
僕の一番大切なもの

授業の前の緊張感にあふれている。この「一番こわい」緊張感は僕にかぎったことではなく、みんなも同様なのだ。だから、「水の泡」などと悲観することはない。最終連の通りさ。
大切なあの人へ 森山 夏紡
(長崎県立希望が丘高等特別支援学校2年)
この詩では
いつも言えないことを書こうと思う
まず出会ってくれてありがとう
今思えばあれは
一目ぼれだったのかもしれない
あなたの幼く愛らしい笑顔に惚れたのだ
今のあなたは一年生の頃に比べると
随分大人っぽくなっている
でも同時に性格も変わったね
嫌いじゃないけどちょっとしつこい
いつも素直になれなくてごめんね
気持ちを分かってあげられなくごめんね
いつも優柔不断でごめんね
勇気を出して想いを伝えた日
返事を待っている間も
どんどん想いが募るばかり
顔も声も髪も体も性格も全部が愛おしい
それに伴って知らない自分を知る
自分が怖い 自分が気持ち悪い
何度も自分を嫌いになった
恋をして涙を流したのは初めてだった
今までも恋は経験したことがある
失恋も経験したことがある
でも涙を流したことはなかった
彼から付き合えないと告げられた
自然と涙が溢れた
それほど彼のことが好きだった
友達になった今でもまだ図々しく好きだ
きっと自分の人生の中で
最も忘れないものになるだろう
私にとっての幸せは
彼が幸せでいてくれることだ
彼を好きになってよかったと心から思う
だから
せめて好きでいさせて下さい

人を好きになることも嫌いになることもある。他人に感情を抱くことは、自分に対して感情を持つこと。恋愛も失恋も人生で何回かある。固定観念に囚われて不自由にならないこと。
追いかけて 山田 竣斗
(見附市立南中学校1年)
追いかけて 追いかけて
形あるもの 手にした瞬間
喜びあふれた 幼なき日
生きることの意味なんて
考えることもなく
ただ ひたすら走った 幼なき日
追いかけても 追いかけても
つかまらない
追いかけても 追いかけても
逃げていく
形なきもの 手にした瞬間
喜びあふれた 今の僕
生きることの意味探しながら
考えて 考えて
ただ ひたすら走る 今の僕

追いかけて「ひたすら走った」、逃げるものを「追いかけ」た。形あるもの・形ないものが何なのか、ここでははっきりとわからないけれど。「ひたすら走る」ことこそ重要なのだ。
こわいもの 吉澤 一葉
(蓮田市立黒浜中学校3年)
小さい頃に怖かった幽霊。
得体の知れないものだから会いたくも見たくもなかった。
今、人間が怖い。
世の中のことを知ったからこそ人間の怖さが引き立つと思う。
戦争で人がたくさん死ぬ
差別やイジメによって死ぬ
思想の違い、文化の違いでの対立
でもしょうがないことだ。
人間は弱い
かぶと虫のような強い角が無ければ蝶のように美しい羽も持たない。
だからこそ人間は知恵を手に入れた。
強い生物や病気には、武器や薬を使った。
だがはるかに強大な生物には人間一人では敵わなかった。
だから群れを成した。
人間は弱いがために群れを成したのだ。
それが今でも続いている。
群れというのは思想が同じ仲間がいること
だから群れ同士での思想の違いで対立がある。
だが理解し和解することもできる
人は幽霊よりも常に見える。
だからこそ話し合い協力し合えれば今の世界はもっと平和になると考えてます。
これからの世界が平和になることを心から願っています。

幽霊よりも人間こそ怖いことを知ってしまった。人は成長とともにそういうことを知ってしまう。怖い人間とも折り合っていかなければならない。話し合い、協力し合えればねえ…
試合の中の一瞬 吉田 智稀
(前橋市立箱田中学校2年)
「バンッ」、空気を裂くような音が
体育館にひびいた。
誰かがシャトルを打った音だ。
そしてそろそろ僕の試合がはじまる。
コールされ緊張しながらコートへ向かう。
そして試合がはじまった。
サーブからはじまるシャトルのやりとり。
相手がネット前にシャトルを落とした。
僕はとっさに前へ動いた。
僕はシャトルに間に合った。
そのシャトルを相手コートの奥に上げる。
しかしそのシャトルは打たれてしまった。
「バンッ」という音をたて、
スマッシュが打たれる。
まるで弾丸のような速度。
レシーブできるかできないかの
重要な局面、緊張の瞬間、永遠の一瞬。
僕は逃さず、レシーブすることに成功した。

バドミントンの試合に出場した、そのようすが克明に描かれる。シャトルを追って機敏に動く、そのさまがよくとらえられている。緊張に満ちた動き、スマッシュの音が聞こえる。
ごめんよりもありがとう 和田 一歩
(十日町市立中条中学校1年)
物を落として拾ってもらったとき
ミスをカバーしてもらったとき
何かを貸してもらったとき
僕は意識していることがある
それはごめんよりもありがとう
ごめんは確かに便利な言葉だけれど
言われるのが僕だったらと少し複雑だ
だってされるなら
謝られるより感謝されたい
だから僕はありがとうと言う
ありがとうは人の心をポカポカさせる
言われる側はもちろんうれしいけど
言う側も相手に感謝を伝えることで
笑顔になれた気がする
ごめんも言っていいけれど
ありがとうは
人を幸せにすると思う
幸せを感じることで周りも笑顔になれる
簡単な気づかいだけれど
それで人が幸せになる
こういう少しの気づかいで
人の心が少しでも温かくなることで
僕のエネルギーになる
それが世界で意識したら
争いをする人も涙を流す人もいなくなる
人が人を笑顔にしつづける世界に
なってほしい

「ごめん」よりも「ありがとう」と言葉を返すのは「謝られるより感謝されたい」からだ。その言葉は人の心を温かく「ポカポカさせる」。なるほど。人がみんな笑顔になれるから。
第32回矢沢宰賞の審査を終えて
異常とも言える今年の夏の猛暑は、みなさんも経験された通りです。海水浴に、花火に、アイスクリームなどに、夏を謳歌したみなさんの元気で賑やかな声が、作品の行間から迫ってくるようでした。たくさんの応募をありがとう! 若者らしく悩んでいても、前向きでした。
常識的に世間的に「暑い!」とただ叫んでいたのでは、常識的で世間的な作品にしかなりません。そこを超えた自分の感性・自分を撃つ固有の言葉で、物事をとらえなくては、作品としての結実は望めません。海水浴や花火にしても、同じことが言えます。
世の常として「常識」とか「通念」というものがあります。それも大事なこともありますけれど、それらにとらわれてしまっては、せっかくの自分の世界を狭く貧相なものにしてしまうおそれがあります。私たちの周囲には多くの言葉があふれていますが、自分の言葉や感性を信じていくことが大切です。「矢沢宰賞」はそのためにもあるのです。
会場で入選者のみなさんとお会いするときが、選者である私にはとてもスリリングな瞬間で、作品と作者が一致します。今年も授賞式に、私は体調が悪くて出席できませんが、選評をくりかえし読んでください。何度も読み返して、選評はみなさんが詩を書くときのエネルギーに負けないつもりで書きました。自分の時間を少しでも増やし、時間を作って詩作にも挑みましょう。
作品すべてに目を通して、最終的にしぼりました。入選の喜びをふくらませ、また選にもれた悔しさを倍の熱情に変えて、根本から詩を愛して書きつづけましょう。
- 審査員 八木 忠栄
1941年見附市生まれ。日大芸術学部卒。
「現代詩手帳」編集長、銀座セゾン劇場総支配人を歴任。
現在、個人誌「いちばん寒い場所」主宰。日本現代詩人会理事。青山女子短大講師。
詩集「きんにくの唄」「八木忠栄詩集」「雲の縁側」(現代詩花椿賞)他多数、エッセイ集「詩人漂流ノート」「落語新時代」他、句集「雪やまず」「身体論」(吟遊俳句賞)。
年ごとの入賞作品のご紹介
| 回 | 最優秀賞受賞者 | タイトル |
|---|---|---|
| 第1回(平成6年) | 山本 妙 | 本当のこと |
| 第2回(平成7年) | 山本 妙 | 災害 |
| 第3回(平成8年) | 高橋 美智子 | 小さな翼をこの空へ |
| 第4回(平成9年) | 野尻 由依 | 大すきなふくばあ |
| 第5回(平成10年) | 佐藤 夏希 | お日さまの一日 |
| 第6回(平成11年) | 除村 美智代 | 大きなもの |
| 第7回(平成12年) | 徳田 健 | ありがとう |
| 第8回(平成13年) | 井上 朝子 | おくりもの |
| 第9回(平成14年) | 藪田 みゆき | 今日は一生に一回だけ |
| 第10回(平成15年) | 日沖 七瀬 | 韓国地下鉄放火事件の悲劇 |
| 第11回(平成16年) | 佐藤 ななせ | 抱きしめる |
| 第12回(平成17年) | 髙島 健祐 | えんぴつとけしゴム |
| 第13回(平成18年) | 濱野 沙苗 | 机の中に |
| 第14回(平成19年) | 田村 美咲 | おーい!たいようくーん |
| 第15回(平成20年) | 高橋 菜美 | 空唄 |
| 第16回(平成21年) | 今津 翼 | 冬景色 |
| 第17回(平成22年) | 西田 麻里 | 命に感謝 |
| 第18回(平成23年) | 山谷 圭祐 | 木 |
| 第19回(平成24年) | 坂井 真唯 | クレヨン |
| 第20回(平成25年) | 宮嶋 和佳奈 | 広い海 |
| 第21回(平成26年) | 金田一 晴華 | 心樹 |
| 第22回(平成27年) | 安藤 絵美 | 拝啓 お母さん |
| 第23回(平成28年) | 宮下 月希 | 大好きな音 |
| 第24回(平成29年) | 宮下 月希 | 心のトビラ |
| 第25回(平成30年) | 阿部 圭佑 | ものさし |
| 第26回(令和元年) | 上田 士稀 | 何かのかけら |
| 第27回(令和2年) | 宮下 音奏 | 大好きな声 |
| 第28回(令和3年) | 横田 惇平 | ふくきたる夏休み |
| 第29回(令和4年) | 野田 惺 | やっと言えた |
| 第30回(令和5年) | 舘野 絢香 | 気持ちをカタチに 思いを届ける |
| 第31回(令和6年) | 青栁 雄大 | 黒板 |
| 第32回(令和7年) | 福井 聖斗 | 最後のステージ |